この記事では、
良いスクールカウンセラーの見分け方
について詳しく説明していきます。
これまでにスクールカウンセラー(SC)について学校プリントで案内を読んだことがありますか?
もしかすると、過去に利用を検討したことのある人や、一度は利用したことのある人もいるかもしれません。
 ゆう
ゆうスクールカウンセラーの知人からは、次のような話をよく聞きます。
子どもの心のケアのために頑張っています!でも、初めての人にとっては抵抗があるみたいです。
「カウンセラー」とか「カウンセリング」と聞くと、「なんだかいろいろ見透かされそうで怖いな。」とか、「相談したって意味ない。」と考える人が多いのかもしれません。
おそらく、スクールカウンセラーについてよく知らないことが原因の一つだと思います。
そこで、今回は、
- スクールカウンセラーについて知りたい!
- どんな悩みを相談できるの?
- 良いスクールカウンセラーの見分け方を教えてほしい!
といった疑問や悩みに答えていきます。
子どもの心理的・発達的な悩みのある方や、スクールカウンセラーに相談しようか迷っている方は、是非参考にしてください。
スクールカウンセラーとは


スクールカウンセラーは、学校で勤務している心理相談に応じる職員です。
子どもの心のケアが主たる業務ですが、文部科学省のホームページでは、スクールカウンセラーの業務について次のように整理しています。
児童生徒へのカウンセリング
教職員に対する助言・援助
保護者に対する助言・援助
学校にどの程度スクールカウンセラーがいるのかは、都道府県や市区町村によって異なりますが、令和3年度の文部科学省の取組として、スクールカウンセラーの全公立小中学校への配置(27,500校)を目標にしているようです。
実態としては、中学校に1~3人程度配置され、そこから近隣の小学校に週1日程度1人のスクールカウンセラーが出張するようなところが多いようです。
スクールカウンセラーが学校にいる日は、中学校では週3~5日程度、小学校では週1日程度になります。
また、スクールカウンセラーは、学校の教員ではありません。
教員とは異なる第三者の立場として、子どもたちの健やかな学校生活をサポートしています。
といっても、スクールカウンセラーが単独で何でもできるわけではなく、養護教諭や学年主任などと連携して、子どもたちの悩みの解決を図っていきます。
後で説明しますが、「いいスクールカウンセラー」の条件の一つに、教員との連携ができているかどうかという点があります。
スクールカウンセラーについては、文部科学省のサイトに詳しい説明があります。
スクールカウンセラーの効果については、次の記事で詳しく説明しています。
スクールカウンセラーってどんな人


スクールカウンセラーは、「心理の専門家」です。
この仕事に就くために必須の資格はありませんが、実質的には、国家資格である「公認心理師」か、心理学系の指定された大学院を修了しなければ取得できない「臨床心理士」のどちらかの資格が求められることが一般的です。



「オンライン心理カウンセラー」や「メンタル心理ヘルスカウンセラー」といった資格がありますが、公的な職場で求められるのは「公認心理師」か「臨床心理士」のどちらかです。
心の問題が多様化・複雑化する現代では、スクールカウンセラーに期待される役割はますます大きくなり、そうした使命感を持って誠実に勤務している方が大勢いらっしゃいます。
しかし、残念ながら、現在の日本ではスクールカウンセラーをとりまく雇用環境や待遇が整備されていません。
そのため、非常勤職員としての採用される人が多く、スクールカウンセラーだけで生計を立てることは難しく、人によっては別の仕事と掛け持ちしている人も少なくありません。
スクールカウンセラーは、大学や大学院を出たばかりの「駆け出し心理士」や、心理相談の職場などを定年退職した後の「ベテラン心理士」などが一定数います。
また、長年にわたって非常勤を続けている「ベテランスクールカウンセラー」や、個人の相談室を開業しながら週1程度はスクールカウンセラーとして働いている「カウンセリングのプロ」といえるようなすごい人もいます。
つまり、スクールカウンセラーといっても、相当に実力のある人もいれば、まだまだ未熟な人もいるなど、個人によって力量は大きく異なります。
ただ、優秀な心理士は、もっと稼ぎの良い仕事に就いていることが多いため、スクールカウンセラーに就いている人の中から、実力のある人と出会えるのはなかなか難しいかもしれません。
といっても、「いいスクールカウンセラー」もたくさんいますので、後ほどその見分け方について紹介します!
どんな悩みの相談に乗ってくれるのか


スクールカウンセラーの業務は、先ほど記載したように、①児童生徒へのカウンセリング、②教職員に対する助言・援助、③保護者に対する助言・援助ですが、具体的にはどのような悩みを対象にしているのでしょうか?
スクールカウンセラーが相談に当たる児童生徒の相談内容は多岐にわたります。
不登校や登校しぶりに関することが最も多いようですが、いじめ被害・加害、友人関係、親子関係、学習関係などの幅広い相談に応じています。
近年では、発達障害、精神疾患、リストカット等の自傷やその他の問題行動など対応が困難な相談も増えてきているようです。
どのような相談であっても対応はしてくれますが、そのスクールカウンセラーの力量や専門性によっては、別の相談できる機関を紹介されることがあります。
学校に通っている子どもについて心理的・発達的・人間関係・問題行動などの悩みがある場合、まずはスクールカウンセラーに相談することをお勧めします。
そのスクールカウンセラーが対応してくれれば継続すればよいですし、もしも対応してもらえないのであれば,専門的な他の相談機関を紹介してくれるはずです。
これも「よいスクールカウンセラー」の条件の一つです!



私の勤めている相談室にも,スクールカウンセラーの紹介でいらっしゃる方は多いです。
よいスクールカウンセラー(意味ないスクールカウンセラー)の見分け方とは


ここまで説明してきたように、スクールカウンセラーは、その個人によって能力が大きく異なります。
また、学校で出会えるスクールカウンセラーは、基本的に1人、多くても2,3人ですので、スクールカウンセラーを選ぶことはほとんどできないのが現状です。
子どもの学校に所属するスクールカウンセラーが、「いいスクールカウンセラー」であれば、悩みの解決に向けて相談を続ける意味がありますし、そうでない「悪いスクールカウンセラー」であれば、早期に相談をやめて、別の専門機関に相談することがよいでしょう。



ここでは「いいスクールカウンセラー」と「悪いスクールカウンセラー」の違いや見分けるポイントについて説明していきます。
子どもや保護者に誠実に向き合ってくれる
スクールカウンセラーとして、心理士として、もっとも大切なことは、相談に来た人に寄り添い、その人の気持ちに共感し、悩みの解決に向けて一緒に取り組もうとする誠実さを有していることです。
よいスクールカウンセラーは、相談に来た人の話にじっと耳を傾けてくれて、そうした人の気持ちや感情について理解してくれて、むやみにアドバイスをせずに一緒に悩んでくれて、相談に来た人に合った具体的な解決方法をいくつか教えてくれるしょう。
一方で、悪いスクールカウンセラーは、相談に来た人の話にじっと耳を傾けてくれるけど、それ以上のことはしてくれなかったり、相談に来た人に好かれようとして保護者や学校の先生の悪口を言ったり、一般的な解決方法しか教えてくれないといったことがあります。
こうしたことについては、実際に直接会ってみて、対面して話してみないと判断しにくいですよね。
スクールカウンセラーに相談しようかどうか悩んでいる人にとっては判断が難しいと思います。



その場合には、そのスクールカウンセラーの予約の状況を聞いてみましょう!
他の子どもの相談で予約が埋まっていて、すぐに相談することができなければ、きっとその人はよいスクールカウンセラーである可能性が高いです!!
相談内容の取扱いについて適切である
スクールカウンセラーには、守秘義務があります。
相談に来た人が話した内容については他の人に勝手に伝えてはいけません。
しかし、スクールカウンセラーは、学校の職員であるので、相談に来た人が話した内容は学校に報告する義務があります。
もしかすると、相談に行く人の中には、学校の教員に不信感を抱いていて、スクールカウンセラーには話せるけど、学校には伝えてほしくないことがあるかもしれません。
そうした場合に、いいスクールカウンセラーは「あなたが心配だから、大切なことは学校の先生にも伝えます。私に何でも話してほしいけど、学校に知らせたくないことは無理して私に話さなくても大丈夫です。」と言います。
相談に来た人の気持ちを大切にしつつ、正直に言ってくれます。
一方で、悪いスクールカウンセラーは、「なんでも話してちょうだい。学校には内緒にしておいてあげるから。」と言います。
その場合、本当に学校教諭に伝えないかもしれませんし、相談に来た人には黙って学校に報告するかもしれません。



心理士でなくても、うそをつくこと、約束を破ることは、もっともやってはいけないことです。
アセスメントとカウンセリングのスキルがある
心理士が相談業務に就くときに、必要なスキルとしては、アセスメントとカウンセリングがあります。
相談に来た人の悩みの原因を特定し,その悩みを解決する方法を見つけ出すもの。面接や心理検査のスキルが必要。
相談者の悩みを解決するための治療的な面接。カウンセリングでは,安易にアドバイスをせず,自分自身の「気付き」を大切にするため時間が掛かる。一方,スクールカウンセラーは,アセスメントに基づいて,その人に合った解決方法を早期に伝えることが求められる。
よいスクールカウンセラーは、このどちらのスキルも持ち合わせているので、相談に来た人にとって最も適した効果的な悩みの解決方法を提示してくれるでしょう。
それも1つだけでなく、最低でも3つほど助言してくれるはずです。
その中から、自分に合ったより良い方法を選択して試すことができます。
悪いスクールカウンセラーは、相談に来た人の話を聞くばかりで、アドバイスをくれません。
心理学用語に「傾聴」と「受容」という重要なキーワードがあるのですが、それを「相手の話を批判せずに、ただただじっくりと聴いてあげること」と誤解しているのでしょう。
また、アドバイスをくれたとしても、一般的な話ばかりだったり、その人に合った方法でなかったりする場合もあります。



これが「相談したって意味ない。」という意見に最もつながりやすいところです。
学校教諭や専門機関と連携を取っている
スクールカウンセラーは、子どもの心のケアが主たる業務であり、子どもと個別に面接することに対して非常に熱心な方が多い印象です。
そのため、スクールカウンセラーによっては、子どもとの面接だけで何とか解決を図ろうとする人がいます。
はたして、それはよいカウンセラーと言えるでしょうか?
スクールカウンセラーだけで解決できるような相談はまれです。



むしろほとんどないと言ってもよいでしょう。
だからこそ、よいスクールカウンセラーは、必ず学校教諭とコミュニケーションを取っていて、同じ悩みや課題を共有しています。
また、よいスクールカウンセラーほど、自分の知らないことや苦手なことをよく分かっていて、相談内容によっては他の専門機関を紹介してくれます。
つまり、よいスクールカウンセラーは、コミュニケーションスキルやコンサルテーションスキルが高いと言えます。
一方で、悪いスクールカウンセラーは、子どもの相談に対して自分一人で抱えて、自分だけで何とかしようとしがちです。
学校教諭ばかりでなく、保護者にも伝えようとしないかもしれません。
これは他の人に、自分が何をしているのかということを知られることで、自分の関わり方を批判されたくないという自信のなさの表れと言えます。
そうした人ほど、自分の専門外の相談であっても、とにかく面接だけで何とかしようとするため、相談が長期間にわたって停滞しがちです。
スクールカウンセラーの役立て方についてまとめた記事もありますのでご覧ください。
おすすめのオンラインカウンセリング
自分のことや家族のことでお悩みの方は、一度オンラインカウンセリングを検討してみてはいかがでしょうか?
他人に相談することに多くの人は抵抗がありますが、私のブログをお読みになっていただいている方は、悩みを解決するために一歩進むことのできる方です。
実際のカウンセリングルームや精神科病院などにいくのは勇気がいりますし、家族の理解も得にくいと思いますので、そうした方には「オンラインカウンセリング」をおすすめしています。
ネットで検索すると様々なオンラインカウンセリングが出てきますが、「うららか相談室」は、私と同じ公認心理師や臨床心理士といった信頼性の高い心理の資格をお持ちの方が相談に乗ってくれます。
多種多様な相談内容にも対応しているので、一度試してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、スクールカウンセラーについて説明し、よいスクールカウンセラーの見分け方について紹介しました。
学校によっては、自分でスクールカウンセラーを選ぶことができないところも多いと思います。
まずは一度利用してみて、そのスクールカウンセラーに相談を続けることがよいのか、それとも別のところに相談に行った方がいいのか検討するとよいでしょう。
私も、スクールカウンセラーさんと一緒に仕事をする機会がありますが、そうした方はみなさん本当に魅力的で、子どものことを一緒に考えようとする姿勢が見られます。
みなさんが、子どもについての悩みが生じたときに、よいスクールカウンセラーと出会えることを祈っています!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
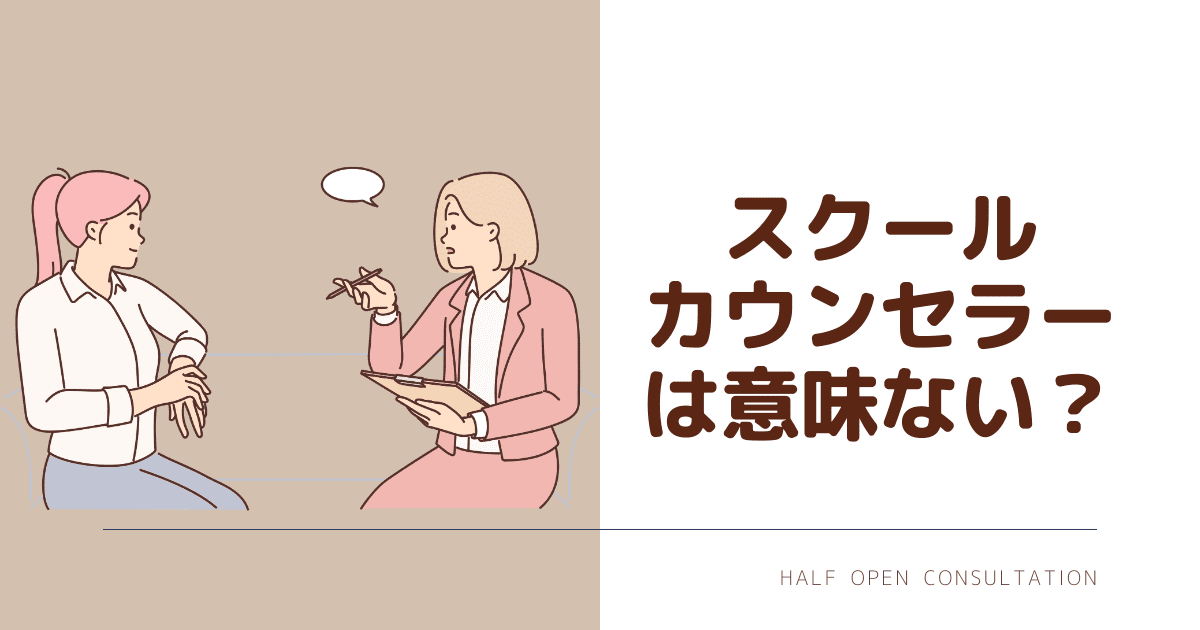

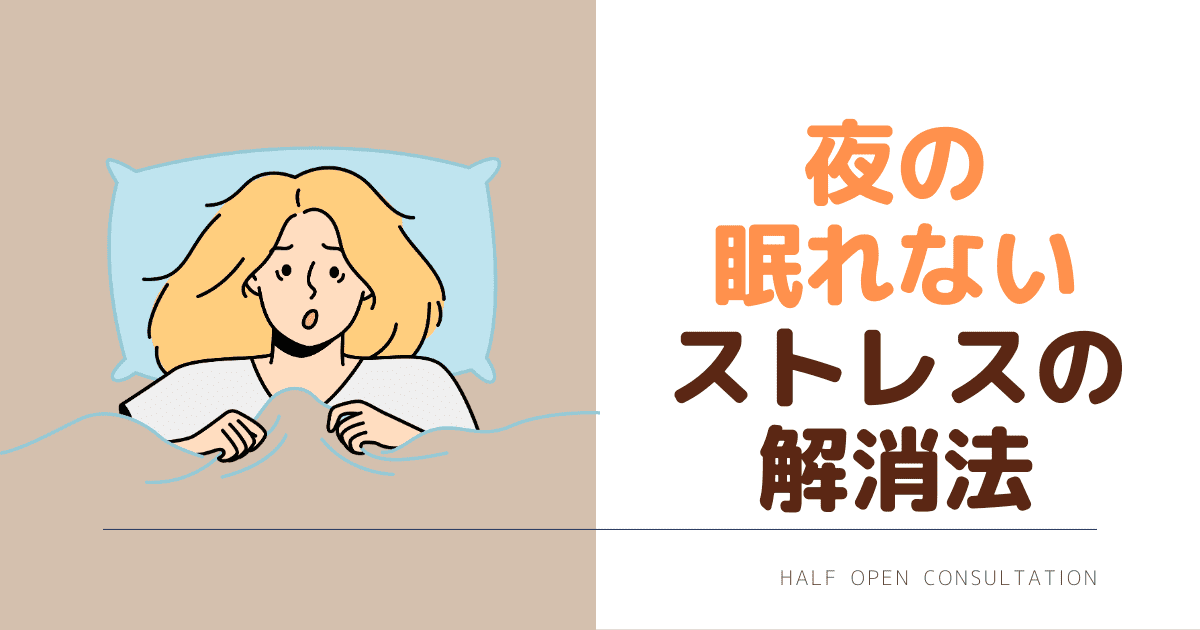
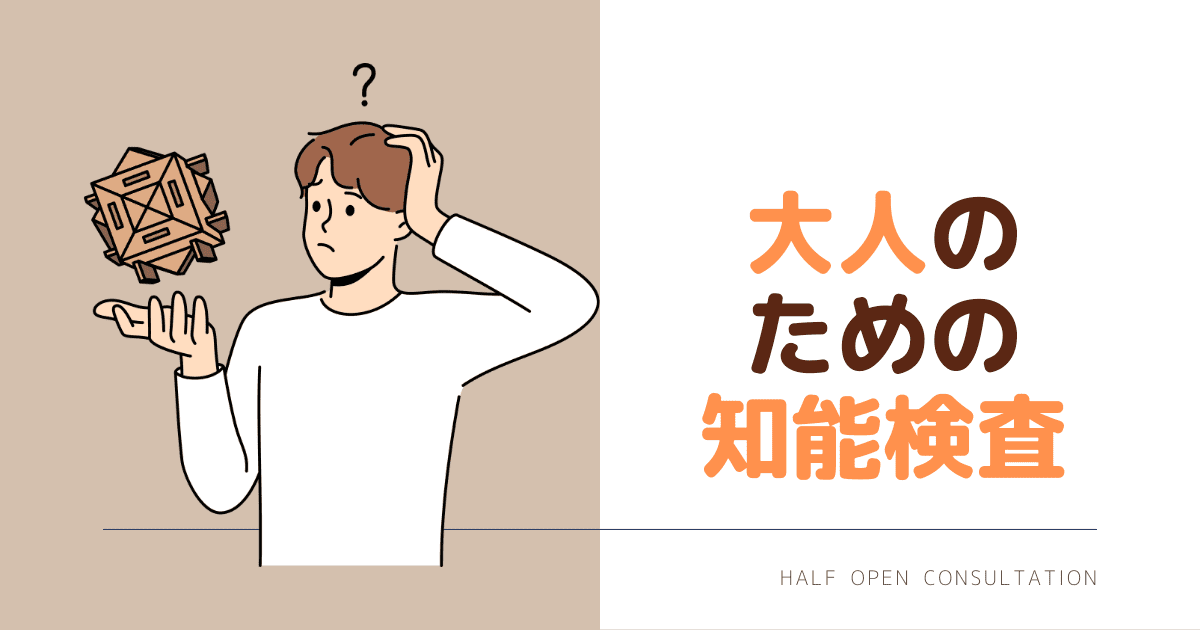
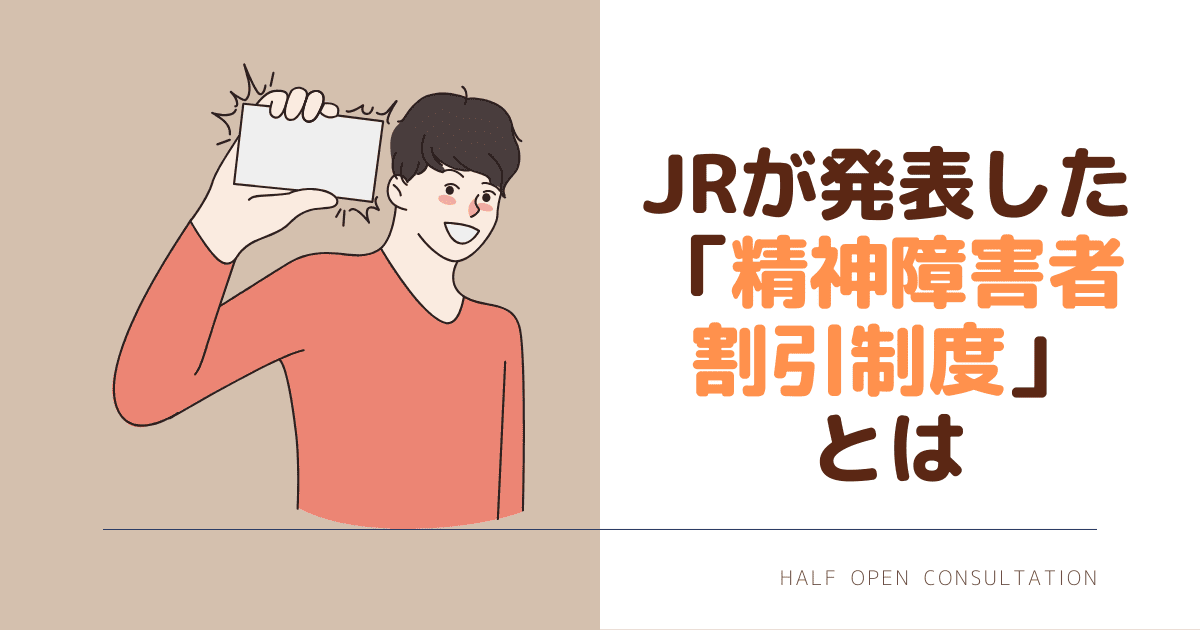
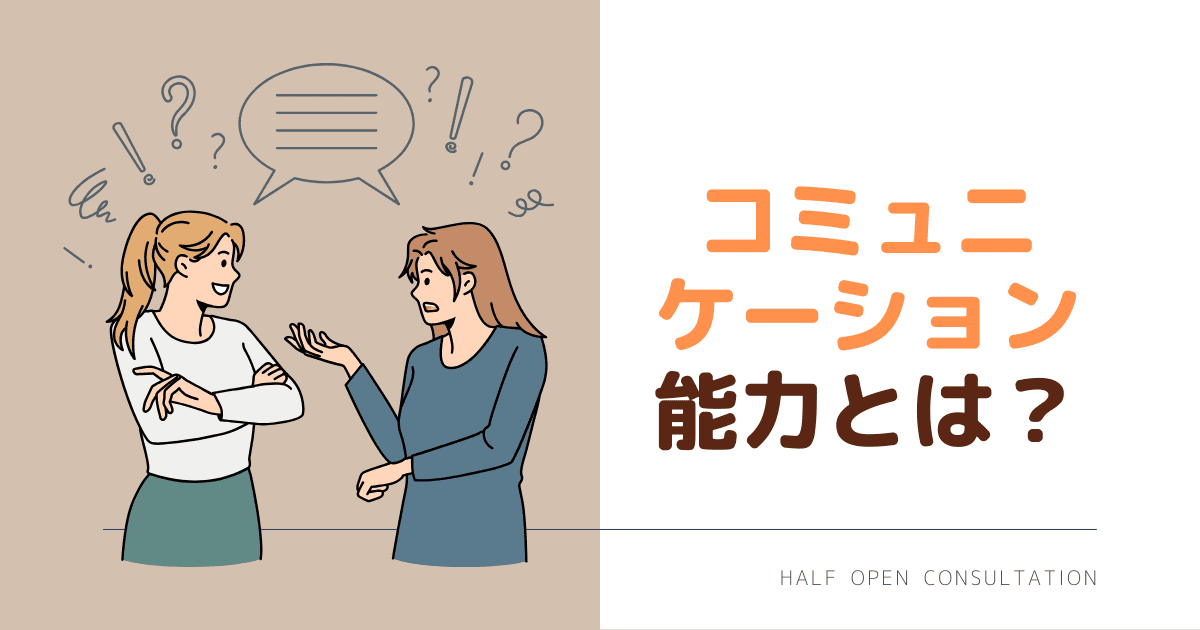
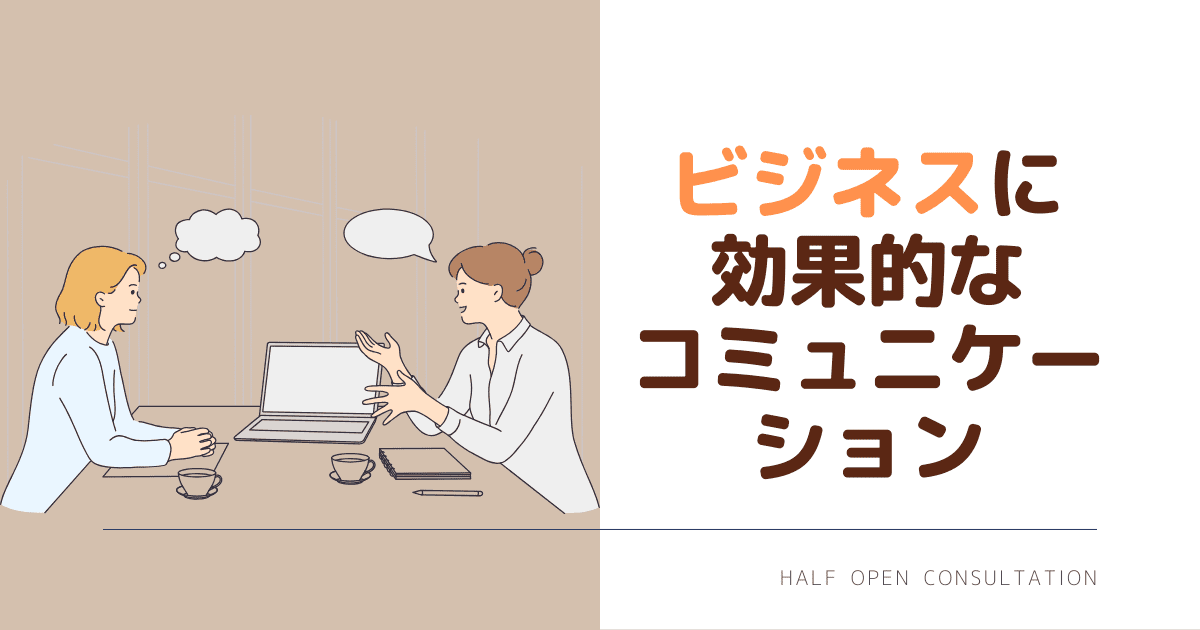
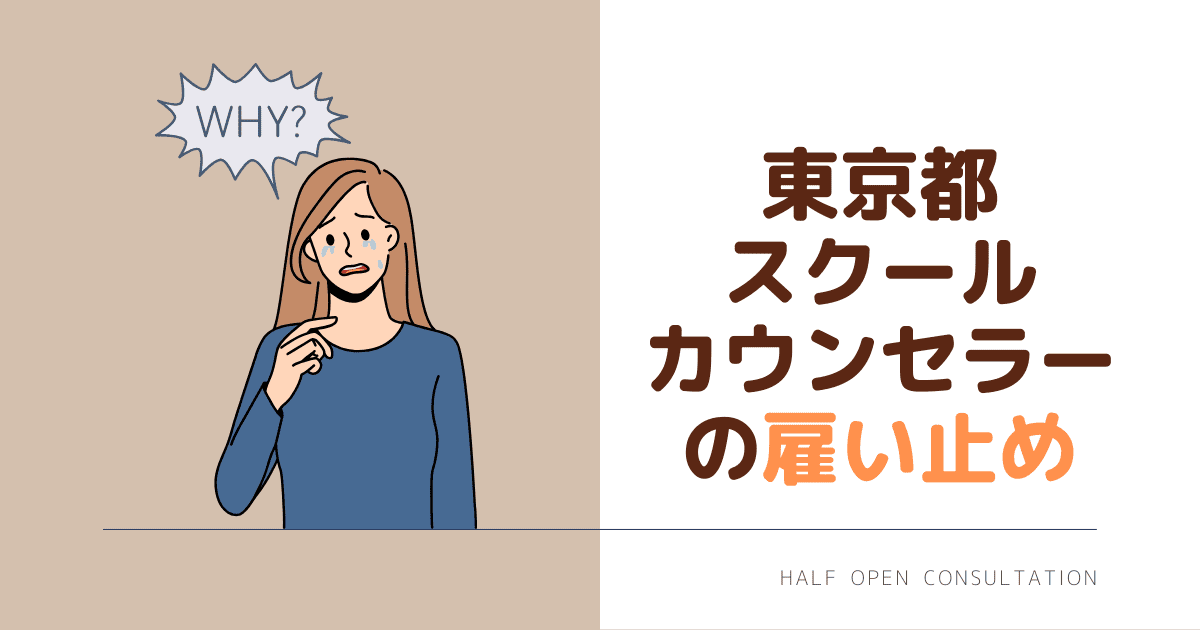
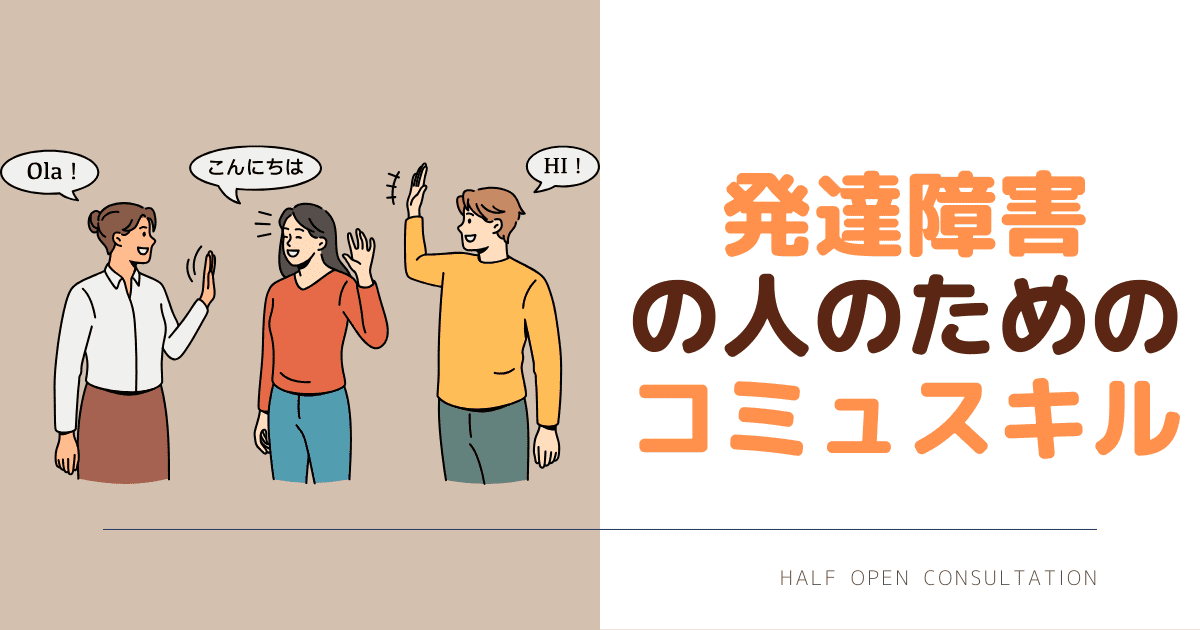
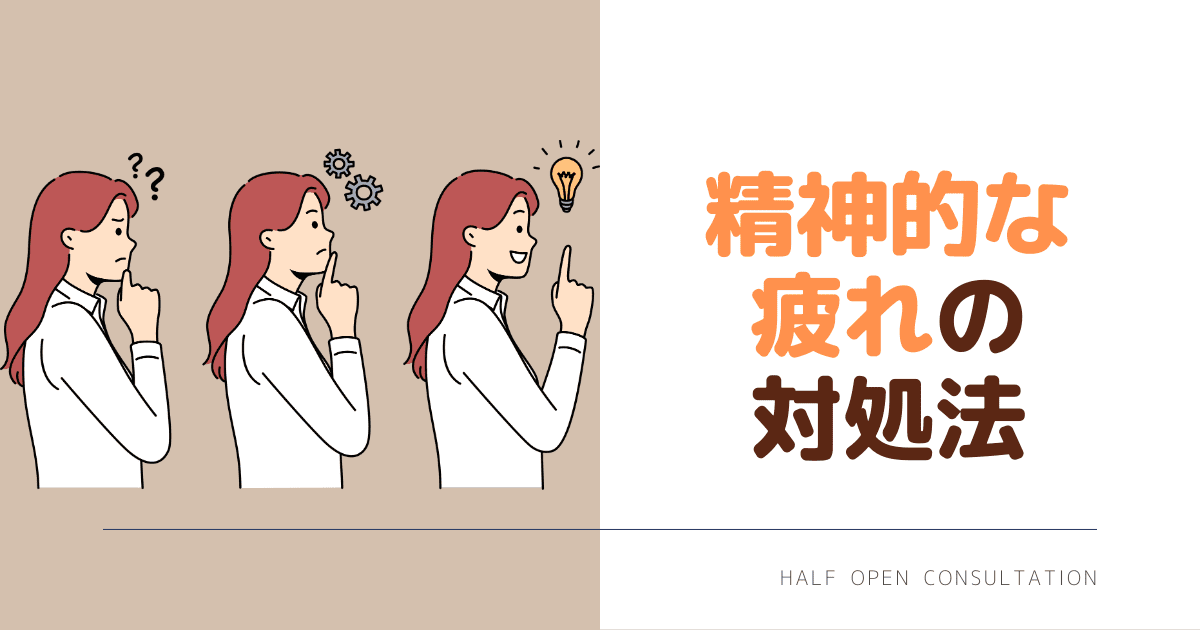
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] スクールカウンセラーは意味ない?良いスクールカウンセラーの見分… […]
[…] スクールカウンセラーは意味ない?良いスクールカウンセラーの見分… […]
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?